特色
大学概要
学部・学科
キャンパスライフ
就職・資格
入試情報
特色
大学概要
学部・学科
キャンパスライフ
就職・資格
入試情報
リハビリテーション学部
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences 言語聴覚学科

高齢者の難聴は緩徐に進行するために自身が難聴であることに気づきにくいという特徴があり、適切な補聴をせずに放置すると認知機能に影響を及ぼす可能性があります。そこで、アプリを使って言葉を聴き取る能力を簡便に測定し、早期に医療機関の受診や補聴器の装用といった適切な支援に結び付けることを目的とした研究です。実際には測定精度や結果の解釈に関する研究を行っています。
一音一音の聴き取り力を測るアプリを用いて高齢者の聴覚機能を測定。聴力に問題のない方のデータを収集し、現時点では未設定の基準値を導き出しています。基準値の設定で対象者への正確なフィードバックが可能に。高齢者難聴の早期発見に役立ちます。


脳が損傷を受けると、「話すこと」「聴くこと」「読むこと」「書くこと」「記憶すること」「注意を向けること」「見た物を認識すること」などの認知機能に障害が生じます。例えば、話すことの障害について、言いたいことが思いつかないのか、思いついたことが言えないのか、言い間違えるのか、その症状は様々であり、それぞれ違うメカニズムで生じていると考えられます。本ゼミでは、患者様の症状がそれぞれの認知機能のどのような過程の障害によって生じているのか、また、それが脳のどの場所(部位)の障害によって生じるのかを、関連病院での臨床活動を通して研究しています。
認知症患者様の記憶や行為、聴覚の障害などを研究しています。毎週、病院で活動を行い、患者様に簡単な検査を行うこともあります。医師や多職種の専門家とのディスカッションで検査結果に関する意見を交わし、チーム医療を実践的に学んでいます。

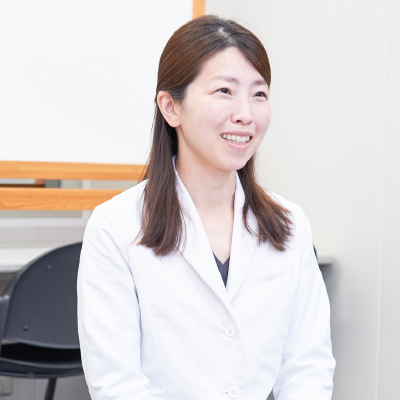
大湊ゼミでは、自然な顔貌や嚙み合わせ、音声言語機能の獲得を治療目的とする「口唇口蓋裂」について研究しています。言語聴覚士は口唇口蓋裂に対し、形態と機能の調和を目指したきめ細かな言語管理を担っています。その支援に役立つ知見を得ることが研究の目的です。一方、口唇口蓋裂に限らず「発音がはっきりしない」「言葉の発達が遅い」「どもる」といった小児の音声言語機能の支援方法も研究しています。これは、音声言語機能の改善だけでなく子どもの人格形成や社会性発達も含めた多方面に関わる研究です。本ゼミは、子どもが好きな人や子どもの発達・支援を学びたい人にも向いていると思います。

田村ゼミでは口腔や喉、呼吸器などの運動障害に焦点を当て、音響学・運動学的な解析手法で患者様や健常者を対象とした研究に取り組んでいます。直接見ることが難しい発話や飲み込みの障害の可視化が、ポイントです。特に発話は聞き手の需要能力で聴こえ方が左右されるため、聴覚心理的な部分にもアプローチしています。近年、科学技術の進歩によってパソコンでの定量解析が低コストで行えるようになっています。本ゼミが得意とするのも、音響分析や動画解析を用いた定量解析です。こうした技術を活用できる言語聴覚士が増えれば、全国どこからでも高水準な言語聴覚療法を受けられる社会になるでしょう。

声や話し方、自分の想いを相手に伝えること、それは自分のアイデンティティそのものです。このアイデンティティが揺らいでしまう、失われてしまう、それが言語障害を抱える患者様の心境ではないでしょうか。本ゼミでは、病気や事故で脳に障害が起きてしまった患者様に対してどのような支援ができるか、また患者様にとってリハビリテーションとはどんな存在かを実際の臨床現場の経験を交えて考えています。研究活動を通して、言語聴覚療法を必要とする方々への理解を深めるとともに、「共感する力」を養い、患者様やそのご家族の気持ちに寄り添って支援できる力を身につけられるようにサポートしています。

私は耳鼻咽喉科の臨床医を務めており、本ゼミでは医学的な方法論を学びつつ研究活動を進めます。耳鼻咽喉科は肩から上の脳と眼以外の領域を診療するため、様々な疾患が研究対象となります。例えば、機能性発声障害という「喉頭疾患」、突発性難聴という「内耳疾患」、耳管狭窄症と耳管開放症という「中耳疾患」、喉頭全摘術という「頭頸部がんの手術」、睡眠時無呼吸症候群という「呼吸器疾患」などを研究して、広い領域に渡る卒業研究論文を作成します。医学研究の進め方には一定の共通原則があるので、ゼミで身につけた方法論を将来の臨床と研究に活かしてほしいと考えています。

自動車運転は、日常生活において欠かすことのできない重要なスキルです。私は、自動車の運転に関係する脳の働きを研究して、リハビリなどの支援を行っています。患者様が仕事や家庭に戻るためにも運転再開は重要なものの一つです。社会復帰に貢献できるやりがいのある分野と思っています。この研究には運転免許センターや自動車教習所との連携が重要で、関係機関といつも連携をとっています。また、医療機関とも連携して研究を行っています。ゼミ生には私の専門にとらわれることなく自分が興味ある分野の研究を後押しして、それぞれの興味を伸ばすことをしています。

障害を抱える子どもたちはもちろんのこと、親をはじめとした家族は様々な苦悩を抱えやすいため、心理的支援の重要性が指摘されています。しかしながら、そのような家族への心理的支援が注目されるようになったのは比較的最近であり、臨床で支援の根拠とすべき理論は定まっていません。そこで、本ゼミでは学内の言語発達支援センターに来所される子どもたちや家族を対象とした心理カウンセリングを実践し、心理的支援の知識・技術の修得を目的に活動しています。このようなゼミ活動を通して、子どもや家族の心と行動が変容していくプロセスに携われることは大きな魅力です。

私は言語発達支援センターで子どもたちの訓練をしており、その中で興味深く感じたことを研究テーマにしています。すなわち、言語症状のメカニズムや改善過程などを客観的に記述・考察することが研究テーマとなっています。訓練に来ている子どもたちの言語症状の改善を実感できることは大きな喜びで、その実感を踏まえたうえで研究できることが本ゼミの最大の魅力だと思います。ゼミ生たちの多くも小児をテーマとした卒業研究を行っているのが特徴です。また、県内の過疎地域へ出向いて「言葉の相談会」の担当をしていますが、この活動は地域が抱える問題点を考える貴重な機会となっています。