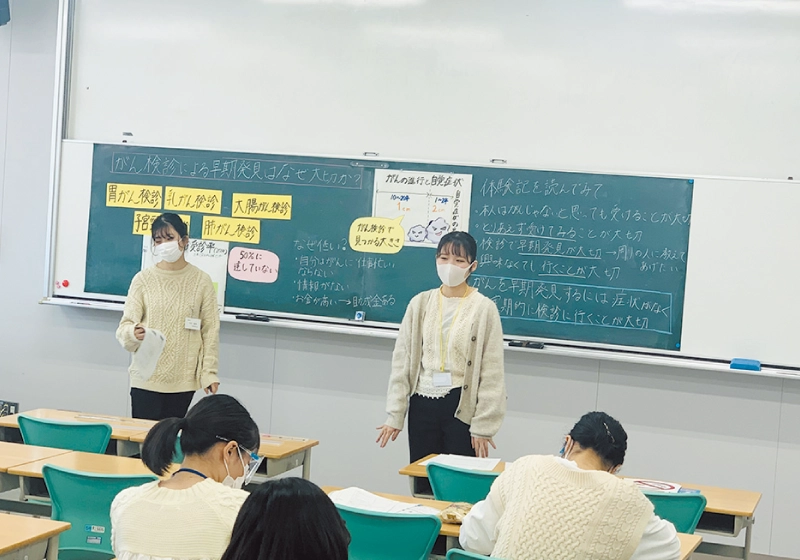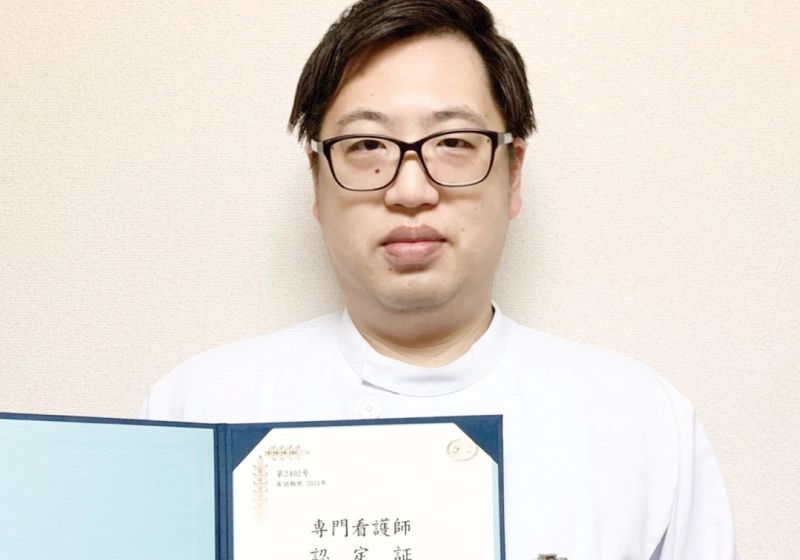全国でも導入例の少ない最新機器を活用した臨床現場さながらのリアルな環境で看護技術を1年次から段階的に学ぶことができるのが最大の特色です。乳児・小児・成人・妊婦の高性能シミュレータは、コンピュータ制御によって涙を流したり、会話ができたりと患者様の様子を表現し、リアルタイムで変化していく臨床現場を再現できます。シミュレータに現れる様々な症状に対して学生自らが必要な看護を考え、それを繰り返し実践し、何度も経験を重ねることで高い看護実践力を身につけていきます。
特色
大学概要
学部・学科
キャンパスライフ
就職・資格
入試情報
特色
大学概要
学部・学科
キャンパスライフ
就職・資格
入試情報