心理学統計法Ⅰ
心理学を科学的に理解し、研究を進めるためには、データの収集や分析が欠かせません。この授業では、データの整理や基礎的な統計分析手法について学び、心理学研究におけるデータの見方や使い方を習得します。実験法や研究法とのつながりを意識し、4年次に心理学に関する卒業論文を書くための基礎的なスキルを磨きます。
心理・福祉学部
Department of Psychological Sciences 心理健康学科
人間や心のしくみなどについて深く考え、心理学を学ぶ基盤を築きます
人間の生涯発達、パーソナリティ、コミュニケーション、認知、学修や動機づけなど「人間とは何か」、「心のしくみはどうなっているのか」について、個人から集団まで人間行動を理解するための基礎的な法則とその応用について学びます。

心理学の基礎を土台として、興味・関心に合わせた領域への学びを深めます
心理学の歴史におけるスポーツ心理臨床の位置付け、発展の経緯を明らかにしたうえで、スポーツ心理学との違いを検討。スポーツ心理臨床の心理支援を理解することで身体を通して心をとらえる視点を身につけ、最善な支援策を考察します。

実習・研究・実験などを通して、人間に対する理解を体験的に深めます
人間行動を実験的に解明するための手法を学びます。また、グループ単位で具体的に研究テーマを決めて質問紙調査を実施することによって、質問紙調査を用いた研究の立案から研究成果のプレゼンテーションに至る一連の過程も学んでいきます。

人間の心理と向き合った4年間の集大成として、卒業論文に取り組みます
保健医療、福祉、教育、司法・犯罪分野の臨床現場に赴き、実習を行います。心理専門家が働く各施設を見学し、クライエントに対する支援、他職種との連携およびチームアプローチ、地域連携、公認心理師としての職業倫理および法的義務について理解を深めます。

| ●必修科目 ●選択科目 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 基礎教養科目群 | ●基礎ゼミ ●情報処理Ⅰ・Ⅱ ●英語Ⅰ・Ⅱ ●スポーツ・健康 ●韓国語Ⅰ ●中国語I ●スペイン語Ⅰ ●ドイツ語Ⅰ ●日本語表現法Ⅰ・Ⅱ ●哲学 ●倫理学 ●ジェンダー論 ●科学論 ●情報科学 ●UROP(研究プロジェクト演習Ⅰ) |
●情報処理Ⅲ ●アカデミック英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ●韓国語Ⅰ・Ⅱ ●中国語Ⅰ・Ⅱ ●スペイン語Ⅰ・Ⅱ ●ドイツ語Ⅰ・Ⅱ ●スポーツ・実践 ●UROP(研究プロジェクト演習Ⅱ・Ⅲ) |
●アカデミック英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ●韓国語Ⅱ ●中国語Ⅱ ●スペイン語Ⅱ ●ドイツ語Ⅱ ●スポーツ・実践 ●UROP(研究プロジェクト演習Ⅳ・Ⅴ) |
●アカデミック英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ●スポーツ・実践 ●UROP(研究プロジェクト演習Ⅵ) |
|
| コアカリキュラム (全学科共通科目) |
保健医療福祉教養科目群 | ●ボランティアの世界
●コミュニケーション学入門 ●対人コミュニケーション論 ●心理学の世界 ●人間を知る ●命の倫理 ●QOLの世界 ●こどもの世界 ●アスリートの世界 ●臨床医の世界 ●加齢と身体 ●食を楽しむ ●眼の神秘 ●義肢装具の世界 ●新潟学 ●国際保健の世界 ●国民の生活と健康を支える仕組み ●現代社会と経済 ●法学Ⅰ・Ⅱ ●臨床の哲学 ●臨床技術の世界 ●留学の魅力 ●シティズンシップ教育入門 ●放射線の基礎と人体への影響 ●新潟水俣病の理解 ●一次救命処置法 ●東洋医学的養生 ●自然人類学概論 ●データサイエンス概論 ●アスリートサポートの世界 ●比較認知科学の世界 ●アカデミック・ライティング |
|||
| 保健医療福祉連携科目群 | ●チームアプローチ入門 ●社会連携実践演習Ⅰ・Ⅱ ●国際交流演習Ⅰ・Ⅱ |
●連携基礎ゼミ ●保健医療福祉連携学 ●社会連携実践演習Ⅰ・Ⅱ ●国際交流演習Ⅰ・Ⅱ |
●保健医療福祉連携学 ●地域連携学 ●連携総合ゼミ ●社会連携実践演習Ⅰ・Ⅱ ●国際交流演習Ⅰ・Ⅱ |
●連携総合ゼミ ●社会連携実践演習Ⅰ・Ⅱ ●国際交流演習Ⅰ・Ⅱ |
|
| 専門科目 | 講義系 | ●心理学概論Ⅰ・Ⅱ ●運動心理学概論 ●心理学研究法Ⅰ ●心理学統計法Ⅰ ●比較認知科学 ●ストレスと脳 ●脳とこころ ●社会福祉概論 |
●心理学研究法Ⅱ ●心理学統計法Ⅱ ●臨床心理学概論 ●精神医学 ●メンタルトレーニング ●スポーツ心理臨床 ●スポーツ心理学 ●スポーツカウンセリング ●アダプテッドスポーツ論 ●精神保健学 ●高齢者福祉論Ⅰ・Ⅱ ●感情・人格心理学 ●知覚・認知心理学(感覚・知覚心理学) ●認知・言語心理学 ●神経・生理心理学Ⅰ(神経心理学) ●発達心理学 ●健康・医療心理学 ●心理的アセスメント ●社会・集団・家族心理学Ⅰ(社会心理学) ●社会・集団・家族心理学Ⅱ(集団心理学) ●社会・集団・家族心理学Ⅲ(家族心理学) ●福祉心理学 ●障害者・障害児心理学Ⅰ(障害児の心理) ●プロセスワーク ●心理的支援法 ●精神疾患とその治療 ●精神分析学 ●健康・医療におけるコミュニケーション論 ●心理療法各論A(認知行動療法) ●キャンプ・カウンセリング ●健康運動心理学 ●ボディワーク ●心理健康科学特別講義A・B・C |
●記憶の科学 ●心理プログラミング ●コーチングの心理 ●競技スポーツの心理学 ●介護概論 ●児童家庭福祉論Ⅰ・Ⅱ ●障害者福祉論Ⅰ・Ⅱ ●神経・生理心理学Ⅱ(生理心理学) ●学習・言語心理学(学習心理学) ●神経生理学 ●認知脳科学概論 ●障害者・障害児心理学Ⅱ(障害者心理学) ●心理療法各論B(力動的心理療法) ●心理療法各論C(自然体験療法) ●教育・学校心理学 ●司法・犯罪心理学 ●人体の構造と機能及び疾病 ●司法精神医療 ●教育相談論 ●青年心理学 ●産業・組織心理学 ●関係行政論 ●公認心理師の職責 ●ブリーフ・セラピー ●学校臨床心理学 ●生態心理学 ●運動学習論 ●ダンス・セラピー ●心理健康科学特別講義A・B・C |
●心理健康科学特別講義A・B・C |
| 実習・演習系 | ●心理学基礎実験 ●心理健康基礎ゼミ |
●心理学実験 ●専門ゼミⅠ・Ⅱ ●心理演習 ●インターンシップ実習 |
●心理実習Ⅰ・Ⅱ | ||
| 卒業研究 | ●卒業研究A・B | ||||
心理学を科学的に理解し、研究を進めるためには、データの収集や分析が欠かせません。この授業では、データの整理や基礎的な統計分析手法について学び、心理学研究におけるデータの見方や使い方を習得します。実験法や研究法とのつながりを意識し、4年次に心理学に関する卒業論文を書くための基礎的なスキルを磨きます。

心理学の知見を生かし、医療や福祉、教育などの幅広い分野で心理支援を行うためのさまざまな方法を学びます。たとえば、「来談者中心療法」や「認知行動療法」などの理論を学び、さらに「ロールプレイング」や「サイコドラマ」などを通じてを体験的に理解を深めます。また、支援を行うときに大切なコミュニケーションやプライバシーへの配慮、心の健康を守る方法についても学びます。

心理的なサポートを必要とする人たちを支えるための様々な知識やスキルを実践的にトレーニングする授業です。具体的にはコミュニケーションの方法や心理検査の使い方、心理面接の進め方、地域での支援の仕組みなどを、事例検討やロールプレイングを通じて体験的に身につけます。また、その人に合った支援計画を考えたり、他の専門職と協力して支援を行う方法を学びます。加えて、公認心理師として大切な倫理や法律の知識も学びます。実践的な学びを通じて心理支援に必要な力をバランスよく育て、4年次の実習につなげます。

心理学の学びの集大成として、自らの関心に基づいてテーマを設定し、研究を進めます。文献調査やデータ収集、分析を通じて、研究を遂行する力を養います。また、卒業研究は発表会で限られた時間の中で研究成果を報告する必要があります。このプロセスを通じて、大学を卒業し、社会人になっても、大学院に進学しても求められる科学的思考や論理的思考、プレゼンテーション能力を身につけることができます。

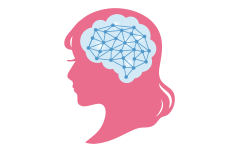
日常生活で用いられている「ストレス」という言葉の歴史や科学的定義を学び、動物を用いた研究や人の基礎的研究から、ストレスと脳の関係やこころとからだの仕組みを理解します。ストレスが生じる仕組みを知ることによって、その対処方法や治療方法を考えていきます。

生物種としてのヒトをよりよく知るために、動物たちの認知の世界を探ることによって、人間の心のより深い理解を目指します。生物の行動に関する基本原理を学び、他の動物の神経系や脳と行動との関連から、種としてのヒトの認知や行動への理解を深めていきます。
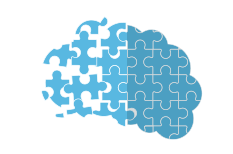
人間にとって記憶はとても重要な機能ですが、同時に忘れること(忘却)も重要な機能です。記憶の種類や健忘症などの記憶の障害について理解を深めるとともに、記憶に関連する脳内メカニズムについても現在までに分かっていることを学んでいきます。

ブリーフ・セラピーというのは、問題の原因が何かを探すのではなく、周りの人も含めてコミュニケーションの方法を変化させることで、問題を解決・解消しようとする心理療法の一つです。そのため、悪循環を断ち切ることや、良い循環を増やしていくアプローチを学びます。
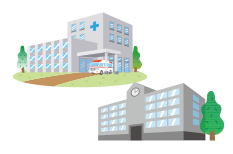
病院、学校、福祉施設、犯罪被害者支援室等の臨床現場で実習を行います。見学による実習を行うことで、クライエントやユーザーに対する支援、多職種連携およびチームアプローチ、地域連携、公認心理師としての職業倫理および法的義務について理解を深めていきます。
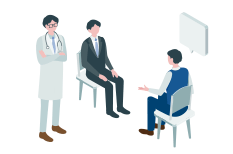
教育や学校現場では、学習障害、不登校、いじめ、非行・暴力行為などの心理社会的な問題が生じますが、その背景を探り、スクールカウンセリングや教育関係者への助言などの支援方法について学びます。また、学校現場における公認心理師の役割についても学んでいきます。

スポーツ選手が練習に意欲的に取り組んだり、試合場面で実力を発揮するために行っているメンタルトレーニングの目的は、自己への気づきを高め、自らが自身のこころとからだをコントロールできるようになることです。その具体的方法について学んでいきます。
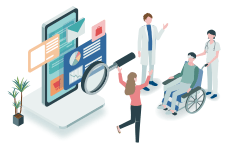
ダンスセラピーは、ダンスや動作で健康を維持・増進・回復し、心身の不調を改善するメソッドです。特に、重症心身障害児・者や身体障害児・者の車椅子ダンスの基礎を実践から学び、個々の身体の可能性とこころの関係性を探っていき、多様な心身の可能性を拓く方法を学びます。

心理発達におよぼす身体運動の影響や、身体運動が不安やストレスに与える効果などを学び、自身の健康増進のための運動処方を作成します。また、認知機能を高める身体運動の方法や、認知障害に対する運動療法の可能性についても探っていきます。