特色
大学概要
学部・学科
キャンパスライフ
就職・資格
入試情報
特色
大学概要
学部・学科
キャンパスライフ
就職・資格
入試情報
医療技術学部
Department of Clinical Engineering and Medical Technology 臨床技術学科

がんの薬剤耐性メカニズムや浸潤転移メカニズムなどを解析し、臨床に応用できるがん克服の手がかりを見出していくことを目標としています。また、医療技術研究では、ペプチドを材料とした副作用の少ないがんイメージング技術や治療薬の開発など、多彩なアプローチでがん医療に貢献することを目指しています。
PARP阻害薬の新たな適用可能性を探るため、DNA修復を行うミスマッチ修復タンパクと、乳がんの治療薬として注目されるPARP阻害薬の関係性を検討しています。この研究を通じて治療薬の新たな可能性を拓き、多くの人の治療に役立てたいと思います。


日焼け止め、マヨネーズ、歯磨き粉・・・共通点は“液体中に粒子が分散している流体”ですが、性質はそれぞれ異なります。大きさ、濃度、などの粒子の特性、液体の種類、それぞれの混ざり具合をコントロールすることで流体の性質がうまれ、それを活用した多くの製品が生活の中で使用されています。人間の血液も血漿に血球が分散した流体といえますが、その流れは非常に複雑で、コンピュータシミュレーションでも完全に再現できていません。粒子分散系は現在進行中の研究ですので、得られた知見が、人間の活動を明らかにする一歩となるかもしれません。
研究テーマは、血液や日焼け止めなど、液体に粒子が混ざった物質の流動特性です。粒子の大きさや形状、濃度、化学構造に着目し、それぞれの特性について調査しています。この調査結果は、未知の部分が多い人間の血流現象の解明に繋がると考えます。


私たちの身近に存在している手洗い前後の皮膚の細菌叢、スマートフォンや不織布マスクに付着する微生物について、プロファイリングを行っています。生活に関係する身近な微生物の研究は、その量に着目した研究は多くあるものの、構成まで詳細に研究している例は多くありません。本ゼミでは、微生物の量のみならず微生物構成の網羅的な解析方法を確立し、実践しています。この研究は、医療現場のみならず、日常生活にも大きな影響を与えうる因子となります。ここに踏み込むことで、生活の質の向上を目指すのみならず、社会的事象をより広く、深く、一般性を持って考察する習慣を身につけることができます。
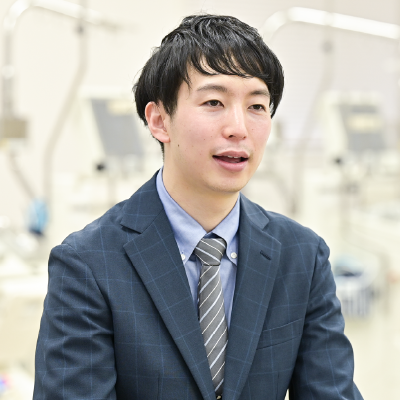
内視鏡機器の急速な進歩により、超音波を発する内視鏡や電気メスと連動した内視鏡治療などが登場しています。そのため、医療現場では、より専門的な知識を有した臨床検査と技師・臨床工学技士が求められています。本ゼミでは、臨床検査技師の微生物学的検査の知識と臨床工学技士の医療機器に関する知識を組み合わせた研究を行います。さらに比較的新しい分野である内視鏡領域でもダブルライセンスの知識を融合した研究を行っているのは、日本国内で本ゼミだけです。実際の機器に触れながら研究を進めることで、内視鏡関連の専門知識を習得した、現場のニーズに即した人材の輩出が可能となります。

2021年の日本の透析患者数は336,179人、新規導入患者数は37,961人であり、その医療費は年間16,000億円、合併症も含めると約2兆円にのぼります。本ゼミでは、患者様に早期に介入し診断・治療を行うことで医療費の削減を行うことを主軸として研究を進めています。尿沈渣検査で尿中に剥離した特異的な細胞に対する抗体を用いて効率的に細胞および細胞の特性を捉え、各種腎・尿路疾患の病態を解明する新たな検査アプローチの開発も目指しています。この研究を通じて、腎・泌尿器疾患で悩む患者様に対して、安価で迅速、かつ質の高い医療技術を提供できるようになると期待しています。

心臓血管手術を受ける患者様や肺機能が低下した患者様は、自身の心臓で血液の循環および肺での酸素化が維持できません。その際に、人工心肺や補助循環と呼ばれる体外循環が使用されます。体外循環は、循環器や呼吸器分野で多く使用され、日本では約5万症例、世界に目を向けると約130万症例が行われており、なくてはならない医療技術です。しかし、一方で様々な合併症を引き起こすことが知られています。本ゼミでは、体外循環中の生体反応のメカニズムの解明や生体適合性が高い機器の開発を行い、より良い体外循環法を提供するための研究を行っています。

『消化器がんをなくしたい!』という究極の目的を遂行するため、新しい予防・検査・治療の3本柱を確立する研究をしています。具体的には、小動物に薬剤や造影剤を投与し、その生体反応をリアルタイムPCR法で評価する実験をメインで行っています。また、私自身、臨床技術学科でダブルライセンスを取得しています。ダブルライセンスを活かし、臨床工学系教員とチームを組み、医療機器デバイス使用下での生体反応をリアルタイムPCR法で評価しています。ダブルライセンスを持つことで、幅の広い実験・評価法に着手することができます。自分の疑問を自分の手で実験し、結果を出す研究の楽しさを感じてもらえるよう指導しています。

IoT(モノのインターネット)で生体の情報を集めAI(人工知能)で解析して体調管理や病気の予防、治療、予後管理に役立てる手法が、医療やヘルスケアの現場に導入され始めています。体調に関するデータは、継続的に追跡しデジタル化することで遠隔診断が可能になるなど利用価値が飛躍的に向上します。本ゼミでは、被験者の負担が少ない測定を可能にする新しいセンシング技術と、集めた大規模データの効果的な解析手法の研究に取り組んでいます。新項目も取り入れた多項目のデータを継続的かつ系統的に追跡することで体調変化を判断し異変を予測・予防することに役立てたいと考えています。

私は、臨床検査の中で、「人間の体が自分でない物(病原体など)を排除する」メカニズムである“免疫”という分野を担当しています。研究は、この“免疫”のメカニズムに重要な認識機構と影響を与える因子、検査法の改良を目的として行っています。一般的に研究の魅力は、未だ誰も見つけていない現象を発見することと言われがちですが、私は、研究の先にある自分の論文が他の研究者の参考となった時に「貢献できて良かった」と思うことに魅力を感じます。研究は、同じ分野を研究している他大学とも連携しながら進め、今後もさらなる発展を目指していきます。

血液透析を必要とする患者さんは年々増加しており、日本ではその数約34万人となっています。血液透析ではバスキュラーアクセス(VA)と呼ばれる血液の出入口となるものが必要になりますが、このVA管理や機能維持は、透析治療を行っていくうえで必要不可欠です。そこで本ゼミでは、透析患者さんにとって命綱となるVAに対して、非侵襲的に管理・機能評価を定量的かつ客観的に行う方法についての研究を進めています。また、近年の医療技術の発達に伴って透析患者さんの寿命も延びてきていますので、将来的には、治療が必要な透析患者の早期発見や、それを判断する医療従事者にも貢献したいと考えています。

病院内で発生する感染症は、医療関連感染症または院内感染症と呼ばれ、治療や手術、医療器材、検査、機器、環境、ヒトなど様々な要因が感染源になります。病院内では医療関連感染を予防するために、微生物学担当の臨床検査技師は医師や看護師とともに感染対策チームを構成し活動しています。本ゼミでは、将来の臨床検査技師が医療関連感染症を減らす貢献をするために、病院環境や医療器具からの感染メカニズムについて研究しています。また、細菌層のバイオフィルムに着目して、生育環境や抵抗性、殺菌等の影響を実験しています。研究を通して、医療関連感染の予防に興味を持つ学生が増えると嬉しいです。

血液中にはエクソソームという小胞が存在していますが、その中に存在する特有な遺伝子を検出して、がんの早期発見に役立てようという研究が注目されています。本ゼミでは、最近開発された血液中のエクソソームからRNA(核酸の一種)を検出する試薬の評価を行っています。この試薬はまだ開発されたばかりなので、病院では一般的に使用されていませんが、将来がんの発見に利用されると考えられています。いずれは、がんの患者様の診断ができるような遺伝子を見つけるための研究に繋げて行くことができる、がんの早期発見に結び付く、やりがいのある研究です。

血液検査学は、貧血・白血病・血友病などに代表される血液疾患の診断、治療効果、経過観察などに欠かせない学問です。また、感染症、悪性腫瘍、肝臓・腎臓などの各種臓器疾患などの検査としても有用です。そのため、血液検査は日常の診療行為に欠かすことのできない基本的な検査です。現在は、自動分析装置を用いた検査が主流ですが、正確な結果を出すためには様々な注意すべきことがあり、誤った結果を出すと誤診を招いたり治療に支障が出たりします。そこで本ゼミでは、正確な結果を出すためにはどうすべきか、誤った測定をするとどのような結果をもたらすかなどを研究テーマにしています。

近年、医療の進歩による医療機器の高度化に伴い、最新の医療機器を安全で的確に操作することのできる臨床工学技士が求められています。臨床工学技士は「人工透析装置」や「人工呼吸器」といった生命維持装置の操作・点検を行います。その中で本ゼミでは、透析治療を行う際に使用する「針の形状」を研究し、患者様にとってできるだけ痛みを伴わない治療方法を確立するために研究を進めています。また、「人工呼吸器」が与える肺への影響を研究することを目的に、豚の肺を使用し設定条件を変化させながら観察・評価しています。患者様の役に立つ研究を、楽しみながら一緒にしてみませんか?

超音波画像診断は、身体に痛みを伴わない非侵襲検査として広く普及しています。検査によって、腹部の疾患を発見することや心臓の大きさや動きを見たりします。しかし、一方で診断装置の適切な設定を怠った場合、あるいは不十分な手技などによって疾患の発見率が低下する恐れがあります。本ゼミでは、医療安全の観点から、患者様に不安を与えない検査の進め方や疾患を見落とさず適切な診断に結びつけるための研究を行っています。また、現在は臨床検査技師が超音波画像診断に携わる機会が多くなっているため、研究を通してゼミ生に検査手技の指導も行っています。